自動車メーカー各社、2022年1~3月期は業績回復ペース鈍化 調達難や原材料高騰 長引く影響
自動車メーカーの業績回復の見通しが不透明になってきた。2022年1~3月期のトヨタ自動車、ホンダの営業利益は前年同期と比べて減益となる見込み。日産自動車は前年同期が営業赤字だったことから黒字に転換する見通しだが、21年10~12月期との比較では大幅減益となる見込み。半導体をはじめとする部品調達難の問題が長期化しており、1~3月期に自動車メーカー各…

ご予約・お問い合わせはお気軽にどうぞ
> ご予約・お問い合せ
TEL : 0120-106-119
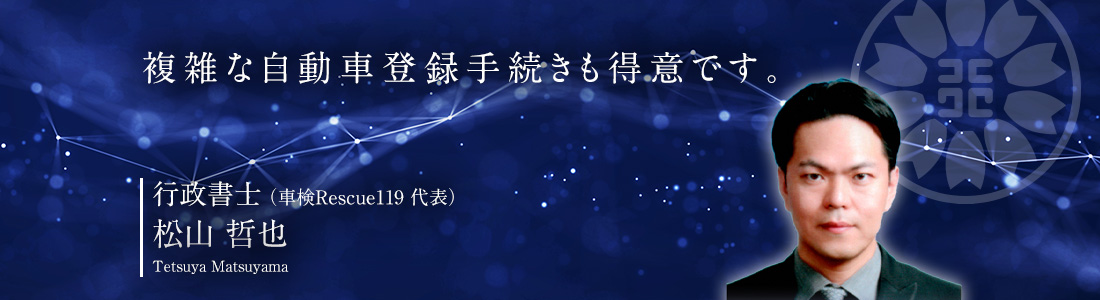
自動車メーカーの業績回復の見通しが不透明になってきた。2022年1~3月期のトヨタ自動車、ホンダの営業利益は前年同期と比べて減益となる見込み。日産自動車は前年同期が営業赤字だったことから黒字に転換する見通しだが、21年10~12月期との比較では大幅減益となる見込み。半導体をはじめとする部品調達難の問題が長期化しており、1~3月期に自動車メーカー各…
自動車安全特別会計の在り方について議論していた国土交通省の検討会は21日、交通事故対策などを目的とする自動車損害賠償責任(自賠責)保険の料金引き上げ幅について、自動車利用者の負担をできる限り抑制するため、年150円以内とすべきだとする中間報告をまとめた。検討会は今秋をめどに具体的な引き上げ額を提言し、政府内の手続きを経て2023年度から新たな保険料が適用される見通し。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012101270&g=eco
普通自家用自動車現在→2万0010円(24か月)
同車予想料金→2万0260円~2万0310円(24か月)
「自動車整備・検査の高度化について」には、国土交通省自動車局整備課の高瀬竜児課長補佐(総括)が登壇。特定整備制度およびOBD検査(OBD車検)について講演した。
副反応なし。
嫁のときは副反応で39度発熱したというのに。
副反応なし。
ごくわずかに注射の場所が凝ってるくらい。
副反応なし。
台風でコロッケ買ってこよう。
嫁の強い勧めと、天皇陛下も接種されたので、私も射ちました!
さて副反応は…?
https://www.youtube.com/watch?v=gIqpz__SlG4&ab_channel=ANNnewsCH
ホンダを主要納入先とするサプライヤー10社の2021年4~6月期連結業績は、全社が営業黒字を確保した。前年同期は9社が営業赤字だったが、コロナ禍からの反動増で売上高が大幅に回復した。ただ、半導体不足の影響による国内事業の回復遅れもあって、通期見通しに対して4~6月期の進捗率は低い。半導体不足の解消のめどが立たない中、7~9月期以降、どこまで巻き返…
https://www.netdenjd.com/articles/-/254132
Q:
5年落ちのホンダN-ONEを中古で購入したばかりです。クルマに詳しい友人から、発炎筒に有効期限があると教えられ、そうとは知らず驚きました。
気になって発炎筒を調べたら有効期限が切れていたのですが、友人から「有効期限が切れていても、車検は通る」と言われたので、そのままなのですが、ちょっと不安です。
(茨城県・24歳・主婦)
A:
発炎筒の有効期限は4年間なのですが、ご友人のおっしゃるとおり有効期限が切れていても、車内に搭載していれば車検は通ります。罰則もありません。
ですが、罰則がないだけで、有効期限切れは要注意です!
発炎筒は、高速道路などで予期せぬ故障や事故に遭遇したときに、周囲や後方へ危険を知らせるために使用する「非常用信号用具」として、重要な役割を果たします。
夜間は200メートルの距離から確認できる赤色の灯光(とうこう)で、雨など悪天候でも5分間燃焼できるなど、発炎筒には基準が設けられているのですが、有効期限が切れていると、炎が暗く小さかったり、水への耐性が落ちて、強い雨だとすぐに消えてしまう可能性もあります。
発炎筒は、カー用品店などで700円から1500円ほどで購入できますが、製品の有効期限を確認しましょう。売れ残っている商品を選ばないように気をつけて下さいね。
https://carcareplus.jp/article/2021/08/12/5259.html